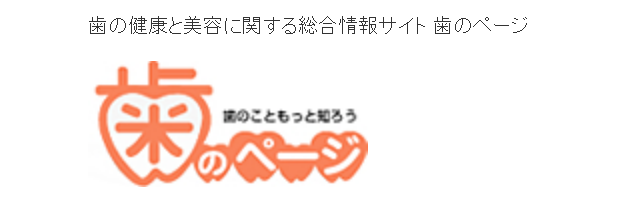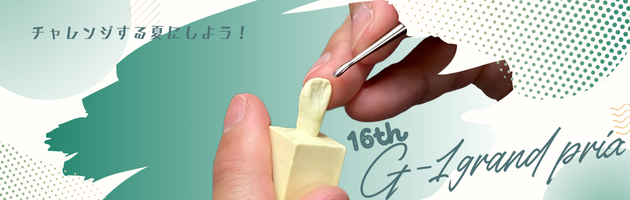最近、米国で16歳の高校生が自殺し、生成AIとの対話が影響したとして、両親が訴訟を起こしたというニュースがありました。映画「ターミネーター」や「マトリックス」の世界の足音が聞こえるようです。
見ず知らずの人のSNS上の言葉を真に受けることも、ましてや人間ではないAIの言葉を根拠に行動することも、私の理解の範疇にないと思っていました。しかしあらためて考えてみると、これまでも本や新聞、テレビの情報を基に判断してきました。そうした情報の発信者に名前や顔があるからといって、友人でも親戚でもない人の情報を信じてきたわけですから、大差はないとも言えます。結局のところ、自分自身の実体験以外の情報を信じるという点では、似たり寄ったりなのかもしれません。
われわれが物を買ったりサービスを導入する際、最初は提供側の情報を信じざるを得ません。提供側の多くは、優位性ばかりを主張し、場合によっては競合品の欠点を謳ったりもします。そう考えるとやはり「複数の知人による評価を情報として集める」あるいは、「複数の類似品を自ら試してみる」といった方法がより良い手段だと言えるでしょう。
歯科技工所のオーナーとしての立場では、複数の器材や手法を内部で試すことができる規模を持つことは有利に働きます。また、歯科医師の先生方に技工製品やその他の製品を提供する立場としては、可能な限り多様な手法や製品を試していただける環境を提供すべきと考えています。現在は、インターネットを通じて膨大な情報が得られる時代となり、展示会や研修会、学会などの場に足を運ぶことを消極的にさせていますが、やはり費用や時間をかけてでも実体験することは重要です。
私も社長職を降りてから、極端に「出不精」になっていますが、それで「デブ症」にならないように、これからは意識して外出しないと……。
和田 主実